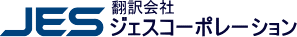Column
| 第77回 抗菌薬と薬の歴史(中編) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <質問> 本羅先生、こんにちは。この間、いつも元気いっぱいの祖母が、何年ぶりか分からないほど久しぶりに風邪気味で、まさか新型コロナに感染したか、いや百日咳か!?と、慌てて病院に連れて行きました。幸いにも色んな検査は全て陰性で、ただの風邪だったようです。ホッとしました。 処方箋をいただいて、薬局に立ち寄った帰り、どうも祖母がプリプリと怒っていて、「どうしたの?嫌なことあった?」と尋ねると、 「なんだい、あの病院の先生は。薬を出すのをケチってんじゃないかねぇ。全然、少ないよ。ほら、抗生物質とかさ、解熱剤とかさ、何もないじゃない。昔は、もっといっぱい薬を貰ったのよ?」 と、まくし立てました。私が、 「えぇ、何それ!? おばあちゃん、そもそも、そんなに熱は高くないよね(苦笑)。薬もタダじゃないんだし、飲まずに済むなら、その方が良くない? 」 と答えたのですが、イマイチ納得いかないようで、ブツブツ言いながら帰宅しました。ていうか、おばあちゃんの若い頃は、風邪くらいで、そんなに、お薬たくさん出ていたんですかねぇ……。むしろ私は、あまり飲みたくないのですけど。 そういえば、本羅先生はコラムでお薬の飲み方を注意されていましたね(第74回)。お薬の話、もう少し詳しく聞いてもいいですか?(東京都 I.K.)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <回答> 1点、ご注意願いたいと思います。私は歴史学の専門家(Historian, 歴史家)や考古学者(archaeologist)ではありません。ですから、前回および以下の解説は、執筆時の教科書レベルで史実とされる内容と私個人の歴史観(historical view) ~ 歴史的見解(historical perspective)というより歴史理解(historical understanding) ~ に基づきます。いかなる思想(thought / ideology)や社会体制にも依存しない「技術史(history of technology)」のように読んでもらえれば助かります。 では、前回の簡単な、おさらいです。おそらく人類は、その誕生に始まる、今から数万年も前から、さらには歴史に続く様々な古代文明においても、しっかり薬と関わってきました。現代に通じる「医学」の扉は、西欧文明の祖たる古代ギリシア文明で開かれましたが、続く古代ローマを境に一旦閉じてしまい、その後しばらく沈滞(ちんたい)します。そこで改めて、古代ギリシア/ローマ社会の詳細から解説再開です。 医学の父ヒポクラテスによる医療の一般化 前回の最後と重複しますが、まずは、古代ギリシアの「医学の父」ヒポクラテス(Hippocrates)です。彼は、多数の患者を丁寧に観察し、症例として詳細に記録しました。そして、個々の事象/経験を一般化する、広い意味での帰納法(induction)で、医療の体系化/秩序化を試みました。それまでの経験則や呪(まじな)いが、「医学」に生まれ変わった瞬間です。特に、個々の病状にとらわれず「身体全体を診る医療」は、現代でも襟(えり)を正すべきところでしょう。 医療の一般化とは、人体の複雑な現象の近似(approximate)とモデル化(modeling)です。そして、平均モデルからの差異で、健康/病態を診断します。 ヒポクラテスの採用したモデルは、「四体液説(humorism)」でした。「身体を流れる4種の体液(血液/粘液/黄胆汁/黒胆汁)の不調和が疾病」という考え方ですね。古代ギリシア社会では遺体の解剖が禁忌でしたから、患者の排泄物や体外への分泌物をヒントにした、現代医学とは相いれない、理念的なモデルであったのは、仕方ないでしょう。 ガレノス登場と瀉血という“誤った一般化”
ヒポクラテスから600年、彼に心酔し、古代ギリシアから、古代ローマ同時代までの医療を、宗派問わず体系的にまとめたのは、名医ガレノス(Galen, ラテン語:Galenus)です。古代ローマ社会でも遺体の解剖は禁忌でしたが、彼は、見世物の戦いで負傷した剣闘士の傷口を「体内の窓」と呼び、人体の解剖学/生理学的な理解を深めました。「心」が「脳」に宿り、「心臓」は「血液を流すポンプ」という現代的な理解は、ガレノスの推測が最初です。 しかし、ガレノスには問題がありました。一部の外傷では、皮下出血した患部を切開し、血腫や滞留した血液の除去で回復を早めます。これを一般化して「体の不調部位における”悪い血液”が疾病の原因であり、その体外への放出が治療になる」と考えたのです。いわゆる「瀉血(Bloodletting, しゃけつ)」です。これは四体液説における「血液の不調和」を改善する意味がありました。もちろん、外科治療(血腫の除去)を内科の疾病にまで一般化するのは誤りです。後述しますが、これは先々に禍根を残す「医療行為」でした。 奴隷制が生んだ古代ギリシア/ローマの学術的発展 少し話が逸れますが、古代ギリシア/ローマでの、学術/文化の大きな発展には理由があります。それは奴隷制(Slavery)です。奴隷の主な供給元は、戦争や略奪による捕虜(ほりょ)でした。平均的な市民は1人あたり2~4人、貴族や富裕層は百人単位の奴隷を所有し、日常の家事/雑事を行う家内奴隷(≒召使)と農場や公共施設で肉体労働する使役奴隷がいたようです。ただし、奴隷の職域は多岐(たき)に渡り、市民の見世物として殺し合う剣闘士を始め、中には下級役人(上級役人の下働き)や貴族の秘書、会計士/教師/医師/建築士など高度な専門職に勤務する奴隷もいます。専門職の奴隷は、敗戦国で専門職だった捕虜や、専門教育を施された奴隷が担い、高給で売買/派遣されました。 奴隷が日常と産業を支えたからこそ、古代ギリシア/ローマの市民、特に自由民(注1)は、それこそ自由に学術/文化を深める時間を得たのです。特に、古代ローマ社会において「自由な精神活動/その産物」は高貴であり、「決まった作業(≒労働)/その報酬」は卑賎(ひせん/身分や品格が低いこと)でした。奴隷の専門職も「高度だが高貴ではない」のです。 ゆえに、今ほど医師は尊ばれず、名乗るに特別な資格も不要でしたから、出鱈目(でたらめ)な医師も多かったようです。ただし、腕が良ければ主任医(ラテン語:archiater, 公的な医師)と認められ、貴族の主治医に任じられると、高位の貴族と同じ特権を得ました。また、公務員としての市医(ラテン語:physicus, 今で言う公立病院の医師)は民衆の投票で決められ、政府からの安定した報酬に加えて、富裕層の診察/治療は高収入でした。もちろん、ヒポクラテスやガレノスは志の高い市民で、自ら患者を治療し、医薬品を調合しました。ただし時代を経ると、薬品の調剤は手仕事で管理が大変なこともあって、「薬種商(pigmentarius, 医薬原料を扱う、薬剤師の前身)」の職域に移りました。
アートの語源とリベラルアーツの本来の意味 ちなみに、ヒポクラテスは「芸術は長く人生は短し / Art is long, life is short. /ラテン語:Ars longa, vita brevis.」という有名な言葉を残しています。これは「医術を修めるには長い努力が必要だが、学ぶ時間には限りがある(だから日々を励むべし)」との薫陶(くんとう)ですが、日本では「優れた芸術作品は時を超えて愛されるが、芸術家の命は儚(はかな)い」と意味の転じることが多いようです。「アート(art)」の和訳が「(観賞目的の)芸術」に引きずられるのでしょうね。元々のラテン語”ars(アルス)”は、ギリシア語”technē(テクネ―)”の訳語です。”technology(テクノロジー, 実用技術の総体)”や”technique(テクニック, 技術/技巧)”の語源ですね。「技術」の意味が強い”art”の類語には、最近流行りの「人工知能(artificial intelligence, 略語:AI)」があります。実際、”art”と対になる英単語は、”nature(自然 /(人の手によらない)それそのもの)”です。つまり「アート」の元々は、語源となるラテン語の「アルス」を対訳したギリシア語「テクネ―」であり、古代ギリシア/ローマにおける「人工物/技術/人が生み出す何か」なのです。 これに、先の「高貴‐卑賎」の価値観を重ねると、古代ギリシア/ローマでは「自由な精神活動」の発露たる「抽象性(abstractness)」が高く評価され、逆に「身体活動/単純作業/労働」といった「具体性(concreteness)」は低く扱われます。よって、非日常的な「アート」は評価/価値が上がります(ここに「(観賞目的の)芸術」が含まれます)。ただし抽象性の高い「アート」は、逆説的に、実務や様々な専門職といった、個々の日常に応用の利く「普遍的な能力」、つまり「本質(essence)」でもあります。そうした、ある意味「万能のアート」こそ、「自由民/解放市民」に求められる、基礎的な教養/能力でした。これが「リベラルアーツ(liberal arts)」です(注2)。現代では、主に「大学で学ぶ一般教養」の意味ですが、「自由な技術/芸術」と直訳しては、本来の意味「市民/自由民に値する者の技能と教養」は理解できませんよね。
古代ローマの衰退:異民族・内乱・皇帝乱立
閑話休題。ガレノスの時代(西暦2~3世紀)、古代ローマは最盛期を迎えると同時に、社会は一気に不安定化しました。原因は外交と内政に分けられます。 外交は、主に異民族問題、特に、北方(ゲルマン人(注3)の南下と侵入)と東方(ササン朝(注4)の敵対)です。 ゲルマン人は、2世紀以降、「フン族(Huns, 現・ロシア中央部/アジアの遊牧民)の西進」と「北部/中央ヨーロッパの寒冷化」で、集落を南下させました(=ゲルマン人の大移動)。さらに東西へ分散し、各集団がローマ帝国の諸地域と接触します。これは「軍事的な侵攻」というより「混乱する隣国への強引な移住」でした。古代ローマ社会はゲルマン人を取り込みますが、逆に、衰退の顕著だった西ローマ帝国はゲルマン人に終止符を打たれました(西暦476年)。以降、ヨーロッパの西側、つまり西欧文明に、ゲルマン人の気風が根付くことになります。 一方、ペルシア地域(イラン高原/メソポタミア)は、紀元前4世紀のアレキサンダー大王による東方遠征(本コラム前回参照)の後、古代ギリシアが実行支配し、古代ローマが引き継ぎました。しかし、東西の古代文明が行きかう交易路「シルクロード(Silk Road)」の中継地として繁栄すると、独立の機運が高まり、特にササン朝は、ローマ帝国に向けて、頻繁に武力抗争しました。
外交問題は、内政の混乱を引き起こしました。「皇帝の乱立」です。 ローマ帝国では、軍隊の最高司令官を兼ねる「皇帝(Roman emperor)」が国家元首ですが(帝政)、それを指名するのは、共和制ローマから続く、代表貴族たちによる統治機関「元老院(Roman Senate)」でした。しかし、皇帝は終身制だったので、失政/悪政を理由に更迭できません。よって、都合の悪い皇帝の排除には、非公式な強硬策が横行しました。 暗殺(注11)やクーデター(注12)です。
異民族との武力衝突が増加し、社会が軍事政権を希求すると、元老院は軍部の強圧に屈して、安易に軍人皇帝を追認しました。ところが、軍部内の権力争いで、不穏なことに、次から次へ皇帝が変わります。不安定な短期政権が連続することで「誰でも皇帝になれるのか?」と皇帝の権威が失墜(しっつい)。挙句(あげく)、元老院の追認すらない「僭称皇帝(tyrant, せんしょうこうてい/僭主(せんしゅ))」が、各地で乱立しました。結果、ローマ帝国は、国土分裂の危機に陥(おちい)ります。 この混乱を抑えたのは、皇帝ディオクレティアヌス(Diocletianus, 在位:西暦284-305年)でした。軍人を内政から切り離し、「官僚」を導入したのです。それを制度化したのが、続く皇帝コンスタンティヌス1世(Constantinus I, 在位:西暦306-337年)でした。官僚制を推し進めて内政を整備し、帝国は再統一されました。ちなみにコンスタンティヌス1世は、東ローマ帝国の行政首都として、自らの名にちなんだ「コンスタンティノープル(Constantinople)」を建設しました。現在でも、トルコ最大の都市かつ欧亜の経済/文化/歴史を誇る「イスタンブール(Istanbul)」として知られます。 多神教ローマにおけるキリスト教の台頭と宗教問題 内政の課題には、もう1つ、宗教問題がありました。 豊かな神話から分かるように、古代ローマの信仰は、多神教でした。しかし、ヘレニズム文化の地域拡大に伴って各地の人々が盛んに往来すると、価値観は多様化し、従来の信仰が薄れて「お祭り/政治的儀式/習慣的儀礼」に形骸化しました。しかし、古代ローマ社会の混乱と不安定さは増すばかり。そこに、新たな「個人の信仰と道徳の規準」を示し「社会(≒所属する生活集団)との一体感」を与えたのが、キリスト教(注13)です。「自由民と奴隷」「貴族と平民(特に貧民層)」の格差が厳然たる古代ローマ社会で「隣人愛/慈悲/慈善/神の下の平等」の教えは魅力的だったのでしょう。ただし、ローマ帝国の公的な宗教行事や奉仕活動を拒否する等、社会秩序を乱すと為政者に判断されると、事あるごとに信徒は迫害(拷問/虐殺/追放)されました。 社会不安を憂いて即位した、先の皇帝ディオクレティアヌスは、軍政の混乱こそ緩和できましたが、宗教問題では失政でした。彼は「社会(≒国家)の一体感」の醸成を目的としたのでしょう。自らを「ローマ神話における主神の子」と称し、市民にローマの神々を崇めるよう義務付けました。「これまでの信仰」を通じた「皇帝への服従と権威回復」を試みたわけです。同時に、立ちはだかる国内の不穏因子として、異教徒のキリスト教(格差社会の否定/他教の拒否)やマニ教(注10, 現世否定)の弾圧を強めました。ときには、見世物として信徒を残虐に殺害したようです。しかし、それまでも為政者から迫害されつつ布教を続けていたキリスト教徒は強く反発し、積極的に殉教(Martyr, 信仰の証としての死)を選び、強い信心を社会に印象付けました。軍でも兵士の反逆/離脱が多発し、宮廷が焼かれるなど、むしろ社会の不安定感は増しました。 そこで、続く皇帝コンスタンティヌス1世は、真逆に方針転換しました。キリスト教に改宗した初のローマ皇帝となったのです。ただし、信仰心は篤(あつ)くありません。東方異民族の各宗教にも好意的でしたし、万人の自由な信仰を認めたのです。結果、相対的に人心は落ち着き、社会の安定が促されました。以降のローマ帝国では、自由になったキリスト教の布教が勢いづきます。そして皇帝テオドシウス1世(Theodosius I, 在位:西暦379-395年)がキリスト教を事実上の国教とすると(西暦392年に他宗教の禁止令を公布)、西欧文明の大きな文化的/精神的な要素として、キリスト教の影響が強まりました。
公衆衛生の後退と医学の停滞 さて、ここまでの説明で、西欧文明(ヨーロッパ)の三大要素 ~ 古典古代(classical antiquity, 古代ギリシャ/ローマ)/ ゲルマン人 / キリスト教 ~ が揃いました。そして、歴史は古代を経て、中世に進みます。 ところで、漫画原作で実写映画化するほど有名な話、古代ローマ人は、お風呂が大好きでした。都市には上下水道と公共浴場が完備され、もちろん、手入れ/清掃が不十分だと感染症の温床になりましたが、基本的な公衆衛生は、高水準でした。また、病人に対しては、滋養と休息を重要とし、健康を身体の「快」と考えていました。しかし、中世では、キリスト教の文化的価値観が広まるにつれ、マニ教(注10)との同時代的親和性もあってか「禁欲/清浄/節制/倫理の堅持」が極端になり、高い精神性と純潔を重んじた「粗食や断食 / 不眠不休の修行(祈祷)/ 性愛の拒否 / 裸体の穢れ」といった志向性は、結果的に、公衆衛生や疾病予防的な生活習慣を廃(すた)れさせました。 また、三位一体の解りにくさ(イエスは神か人か?ヤハウェと別の神なら一神教ではない?など)もあってか、キリスト教内での教義を巡る異端(heterodoxy)と正統(orthodoxy)の論争は、ローマで布教が進む初期からありました。結果、現在でも「カトリック教会(Catholic Church, 西方旧教とも)」「プロテスタント(Protestant, 西方新教とも)」「正教会(Orthodox Church, 東方とも)」に代表される幾つもの教派(denominations)に分かれています。この点ではマニ教と逆に、キリスト教徒の異端/異教への不寛容さ/攻撃性は大きく、信仰の禁止(破門)/処刑/追放が繰り返されました。 東方への頭脳流出とイスラム世界での医学発展
異端とされたキリスト教徒はローマ帝国を離れ、多くは東進してイスラム社会に紛れました。帝国化したイスラムは、他の一神教教徒(ユダヤ教/キリスト教/ゾロアスター教/マニ教など)を「同系統の不完全な宗教(注5)」と見做し、ジズヤ(Jizya, 人頭税)を払えば、弾圧しなかったのです。また、専門職の従事者には、信仰を問いませんでした。その結果、ペルシアやローマ帝国に残されていた、様々な古典古代の文化遺産(もちろん、ヒポクラテスやガレノスも)が、さらに東方のインド/アジアの文化とともに、イスラム社会で集積し、発展します。また、ササン朝に代わる東西文明との交易による、多彩な物資の流通は、薬種商の活躍を促しました。イスラムの医師たちは、ガレノスや四体液説を超える新たな医学を産むには至りませんでしたが、医学書/薬学書をアラビア語に訳す中で理論的考察を深め、得られた医術を実践しました。 一方、まさに「頭脳流出(brain drain / Human capital flight)」のヨーロッパです。教会内の規範が、信徒を通じて世間に浸透し、社会の一般常識として定着するという意味で、キリスト教は大きく影響します。聖母マリアの処女懐胎や、生前のイエスが起こした「病人の癒し」など数々の奇跡があってか、疾病は「神の罰/悪魔憑き」などと解釈され、祈りや儀式で治そうとするなど、医療水準は古(いにしえ)に翻(ひるがえ)り、体系的な医術は異端視されました。ここで、古代ギリシアにおける医学/薬学の萌芽は、萎(しお)れます。 修道院が守った“医学の苗木”と病院の原型誕生 とはいえ、現代的な医療/看護の、少なくとも発想の一端は、キリスト教の「異教徒にも与える慈善」に基づいています。信仰に身を捧げる修道士/修道女(Monk/Nun, 修道者とも)が、ともに祈り/学び/労働する、自給自足の共同生活施設である修道院(Abbey, もちろん男女別)には、修養/修行の設備とは別区画に、巡礼者の宿泊/社会的弱者の援助/患者の治療に用いる施設が用意されました。規模によっては、隣接して「救貧院(almshouse, きゅうひんいん)」や「施療院(hospice, せりょういん)」を建てています。これは、ラテン語の「客を迎える場所(hospitium, ホスピティウム)」に由来する施設で、現代の「病院(hospital)」の原型です。施療院での聖務には、医師/看護師としての役割が求められますから、少しでも患者を癒そうと、原始的な民間療法に加えて、(学問としては異端になるため)図書室で埃をかぶるヒポクラテスやガレノスの医学書を実用書として使い、庭では食料と共に薬草を栽培しました。結果的に、「医学」の苗木は、わずかながら教会に残されたようです。
おっと、ようやく中世に差し掛かったところで、字数が大幅に超過です。今回は、医学/薬学というより、近代科学の根幹にある西欧文明を根っこから理解するべく、背景の説明が多くなってしまいました(むしろ、そっちが中心?)。しかし、現代の科学文明につながる大海の、複雑かつ大きな流れは、何とか泳ぎ切れたと思います(まだ沖で溺れているかも?)。 次回は、完結編として、中世から近代を駆け抜け、現代の薬学まで辿りつきたいと思います。もちろん、過去の本コラムで触れていることは参照しますから、多分、大丈夫でしょう(?)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||